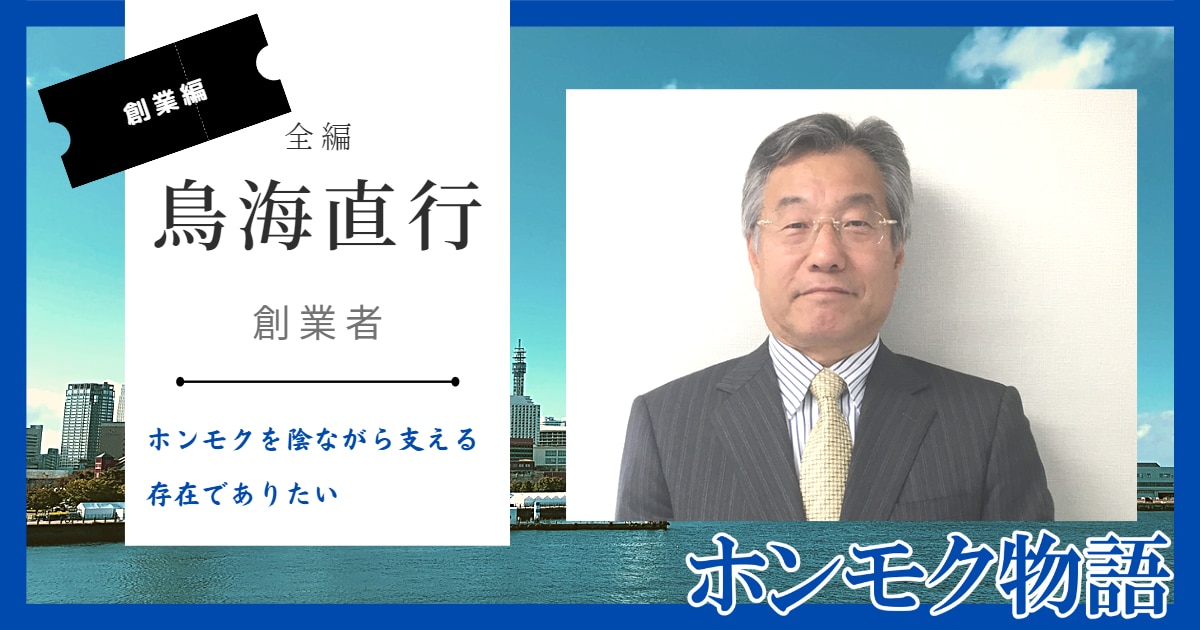
インタビュー 「ホンモクを陰ながら支える存在でありたい」創業者 鳥海直行
目次[非表示]
生い立ち
私の生まれは川崎の元住吉です。姉と兄、そして末っ子の次男として育ちました。
小学生の頃から将来は起業したいという夢がありました。
その夢を叶えるため、社会人になり様々な職を経験するなかで、初期投資の少ないメンテナンス会社なら自分でも起業できるかもしれないと思いました。
そして、学生時代のアルバイト先であった日本橋のビルメンテナンス会社へ就職。その当時はちょうどディズニーランド開業のころで、テーマパーク裏に建設されたホテル共有部の清掃部門の統括者を任されました。
その後、「マイカル本牧」の建設に伴い異動。立ち上げから携わり、自宅へ帰ることもできないほど多忙で、根岸に単身赴任をしながら仕事に明け暮れる日々でした。日中は日常清掃、夜は定期清掃。昼夜、延べ70人を束ねる責任者を務めていました。
そうした経験から、そろそろ自分でも起業できるかもしれない、と35歳で独立。それが平成2年です。
当時はバブル経済の終焉でしたが、みなとみらい地区の建設ラッシュだったこともあり、飛込営業や電話で、とにかくバンバン、自ら新規受注をしていきました。
新築工事中ビルで職人さんが作業した後の清掃業務が主で、抱える人材はアルバイトだけでも70人程。日当で現金を即日支給するので、資金繰りがとにかく大変でした。
その建設ラッシュも3年程で落ち着き、「さてこれからどうしようか」と。それで「日本橋のビルメンテナンス会社の事業であった日常清掃や定期清掃を自社に取り入れよう」と事業シフトしていったのです。
私が40歳のときでした。
更なる試練が待っていました...
日常・定期清掃へシフトして2年後です。
当時は正式な契約書を交わさない仕事もあったので、或る案件で入金がなく、その社長宅を訪ねたらもぬけの殻だった。つまり夜逃げされてしまったのです。200万円の損失でした。人件費をプラスすれば被害はより甚大です。
ショックでしたね。
経営の厳しさを痛感いたしました。
その出来事を機に一点集中型の経営から、顧客数を増やすリスク分散型の経営手法に切り替えたのです。とにかく、利益率維持のため必死に業務を続けること8年。その後、更なる試練が待っていました。
長年お付き合いのあった信頼できる方から、自動車部品の金型を製造する会社の代表を任されたのです。本業との二足のわらじでした。
当初は順調でしたが、その方が突如、心筋梗塞で倒れ、金型の仕事ができなくなってしまったのです。私はその会社の連帯保証人でしたので、銀行からの融資残約500万円も負うこととなりました。連帯保証人という立場を軽んじていたのかも知れません。
まさか、大病を患われるとは…予測もできませんでした。
経営者として、勉強不足ではいけない、健康でなければいけない、と改めて肝に銘じたのです。
そして再び新規営業で、施設のリニューアル工事や設備・電気一式交換工事を受注しました。
不測の事態に遭うたび、「なんとかなる」という強い精神力で乗り切るしかなかったですね。
オンとオフで頭を切り替え、仕事へのモチベーションを自ら保っていました。
方針固め、決断の時
融資残の返済後、2000年に施行運用された介護保険制度によって、当社も将来の高齢化社会を見据え、本業のビルメンテナンス業と併行し、アイ・ティ・ケー有限会社を2002年に設立。介護事業へ新規参入を果たしました。
主な業種は訪問介護と介護タクシーです。
介護タクシーの運転手を務めるため、私自身も普通自動車第二種免許と介護ヘルパーの資格を取得。根岸のビルメンテナンス業は二名の責任者へ任せ、朝と夕方に利用者様の送り迎えをしていました。
ただ、利用者様が病院や施設にいる日中の時間帯はあまり仕事がないことと、ケアマネージャーへ直接営業をかけても、当社のような新規参入には充分な案件が回ってこなく、人材も次々と辞めていく悪循環が続きました。
それでも利用者様から、「ありがとう。助かるよ」と毎回声をかけてもらえる事にやりがいを感じていたのです。
しかし、こうした感謝の気持ちをいただくのと、会社経営とは別物だ、とつくづく感じました。
実際4年間で介護事業への投資は2000万円ほど。その経費は本業のビルメンテナンス業の売上に、私自身の給料の投資でまかなっていたのです。そして遂に2006年10月、介護事業から撤退。
本牧ビルサービスとアイ・ティ・ケーを併せて、ビルメンテナンス業を強化する方針を固めました。
介護事業は経済的にはマイナスでしたが、精神的には大いにプラスな面を残してくれました。
今でも介護事業へ参入したことを全く後悔はしていません。そのときに培われた「感謝の心」が現在、当社の理念のひとつである「人にやさしい社会を創る」へ繋がっているのです。
その後、資本金を自己投資で1000万円から2000万円へ増額。より大規模な仕事を受注していく方針を定めました。主な事業であった清掃業だけでなく、設備管理までの建物総合管理を行っていくことを決めたのもその頃でした。
未来に向けてプラスの努力
介護事業から撤退後、基盤の清掃業を柱に設備管理業へ事業を拡げました。
根岸社屋が手狭になったこともあり、敷地面積200坪の保土ヶ谷区桜ヶ丘へ社屋移転をしました。当時は自社スタッフで受注から管理、施工まで、すべてを担っていたので、低コストが実現でき利益率は上昇しましたが、人員不足による新規アルバイトの増員で、却って技術面の質は低下。取引先様からクレームが出るなどの問題点が浮上してしまったのです。
加えて、残業代等の人件費も嵩み、利益率をいくら上げても売上げは平行線のまま…という一長一短の経営が続きました。
「このままでは会社のプラスにならない」と協力会社を募り、プロ作業員へ委託することで仕事の質を安定させる方向へと転換しました。
と同時に、それまでの経営方針が、わたし自身のいわゆる「勘ピューター」だったので、将来を見据え、より組織化を図るべく、神奈川県中小企業家同友会の勉強会へも参加し始めました。そちらで学んだことをベースに、第23期にあたる2012年3月より導入したのが手帳式の経営計画書です。経営手帳をつくることで、年次ごとの経営目標が明確化され、先々の見通しが立てられるようになりました。
しかし、経営手帳は当初社内では浸透しづらく、週一回ペースで粘り強く幹部役員と会議を重ね、徐々に理解を深めてもらえるよう努めました。
そして、わたしが50歳を過ぎた辺りからでしょうか。一代でこの会社を終わらせたくない、と強く意識するようになったのです。
『大企業にしたい』とまでは考えませんでしたが、ホンモクを継承していってもらうことは、自らが生きてきた「証」を印すことでもあると思いました。
そして、世代交代を徐々に考えるに至ったのです。
ホンモクを陰ながら支える存在でありたい
仏向町へ移転後、まず着手したことはリスク分散型経営でした。
清掃部門が売上の大半を占める中、設備にも力を入れつつ、別の柱となる新事業を創設しようと思いました。その頃、取引先よりホテルのベッドメイクのお話を頂戴したこともあり、将来的なインバウンド需要が見込めるホテル管理事業部を立ち上げました。
そして2019年、わたしが65歳のタイミングで現社長と世代交代をしました。
会長となった現在は、週一回の役員会議に出席すること以外は、ホンモクの経営に直接的な関与をしないようにしています。
わたし世代と現社長の世代とでは社会情勢や時代感覚も異なるからです。
今は同世代の会長職の方々と勉強会や意見交換会を行う他、関東学院大学や横浜商科大学で企業経営の講義もしています。日本企業の99・7%が中小企業である現状を学生の皆さんへ伝え、就職活動に活かしていただきたいと思っています。
その中で一番強く語ることは、「常に感謝の気持ちを忘れない」という姿勢です。
現社長への期待は、如何なる環境下でも安定してゆける企業へとホンモクを成長させてもらうこと。
社長という職は社内での役割の一旦であり、立場が偉いわけではありません。
常に明るいモチベーションで、社員がなんでも打ち明けられる人柄であってほしいと願っています。
ITが加速する中、今後のビルメンテナンス業界はどうなるのか。AIによる清掃業やメンテナンス業も急増していくでしょう。そうした中で人間には何ができるのかを目下模索中です。
その上でわたし自身は、いまのホンモクを陰ながら支える存在でありたいと考えています。


